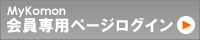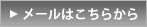作成日:2025/09/01
【採用定着コラムVol.17】リーダーシップとマネジメントスキルの評価
【中小企業の中途採用が成功するためのポイント Vol.17】
全24回にわたって、中小企業の中途採用が成功するためのポイントについてわかりやすくお伝えしていきます。一気に改善は難しいので、コラムの内容をヒントに「少しずつ」の改善を目指していきましょう!
≪本日のテーマ≫
第17回「リーダーシップとマネジメントスキルの評価」
________________________________________
中途採用者にリーダーや管理職候補を求める企業も多いなか、「どのようにリーダーシップやマネジメントの力を見極めればいいのか」と悩む採用担当者は少なくありません。
これらのスキルは、職務経歴書や面接だけでは判断が難しく、採用後にギャップを感じるケースもあります。
今回は、中途採用者のリーダーシップ・マネジメントスキルの評価方法や見極めのポイントを解説します。
________________________________________
〜リーダーシップスキルの評価方法〜
(1)実績だけでなく「行動の背景」に注目する
「プロジェクトリーダーを務めた」「チームをまとめた経験がある」といった実績は一見魅力的ですが、重要なのはそのとき“どのような行動を取り、どんな影響を与えたか”です。面接時には、「どんな課題に直面し、どのように周囲を巻き込んだか」「部下や同僚との関係構築において意識していた点は?」など、エピソードを掘り下げて確認しましょう。
(2)リーダーとしての姿勢や価値観を問う
リーダーシップには「目標達成志向」「人材育成への意欲」「信頼関係の構築」など、いくつかの重要な姿勢や考え方があります。面接では、「どんなリーダーを目指しているか」「理想のチーム像とは何か」といった質問で、本人の価値観を確認するのも効果的です。
(3)実践的なケース質問を活用する
「こんな場面で、あなたならどう対処しますか?」というケーススタディ形式の質問を活用するのも有効です。例えば、「納期が迫る中、メンバーのモチベーションが下がっている場面でどう対応するか」といった質問を通じて、判断力や対人スキルを評価できます。
________________________________________
〜マネジメントポテンシャルの見極め方〜
(1)数値管理と人材マネジメントのバランスを見る
マネジメントには、目標管理や進捗管理といった“数値面”と、人材の育成やチーム運営といった“対人面”の両方が求められます。職務経歴書で成果を確認するだけでなく、「部下の成長をどう支援してきたか」「メンバーとの関係構築で苦労した点とその対処法は?」など、行動や考え方の両面から見極めることが重要です。
(2)コミュニケーション力に注目する
マネジメントにおいて、的確な指示だけでなく、周囲との信頼関係づくりやフォローアップの力も欠かせません。面接のやりとりや適性検査の結果から、相手の話を引き出す力や説明のわかりやすさ、傾聴の姿勢などを確認しましょう。
(3)将来性を見る視点を持つ
マネジメント経験が浅い場合でも、「過去にどんな役割を担ってきたか」「周囲からどんな人物として評価されているか」などを聞くことで、ポテンシャルを判断することができます。また、既存社員と同様に適性検査を活用し、組織風土やポジションとのマッチ度を見るのも一つの方法です。
________________________________________
〜採用後の育成も前提にする〜
(1)完成されたリーダー像を求めすぎない
中途採用といえど、最初から「理想的なリーダー・マネージャー」である人材は多くありません。採用時点では、「一定の素質と伸びしろがあるか」に注目し、入社後にどのような成長支援ができるかという視点も持ちましょう。
(2)入社後のトレーニング環境を整える
管理職としてのスタートを支援するために、社内のマネジメント研修やOJT制度の整備も大切です。役割や責任の明確化、期待される行動の共有を通じて、本人が力を発揮しやすい環境を整備しましょう。
________________________________________
≪本日のまとめ≫
リーダーシップやマネジメント力の評価は、経歴や肩書きだけでは判断しきれない繊細な分野です。応募者の言動の背景にある考え方や行動特性に注目し、実践的な質問や適性検査などを活用して多角的に評価することが重要です。さらに、入社後の育成も視野に入れて、ポテンシャルを重視した採用を行うことで、長期的に活躍できる人材を確保することができます。ぜひ今回のポイントを参考に、自社に合ったリーダーの採用と育成に取り組んでみてください。
________________________________________
*次回は、第18回「チームとの統合と協力体制の構築」についてお伝えします。